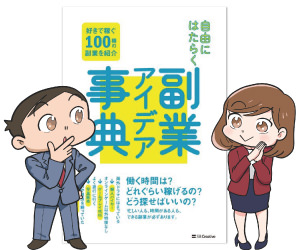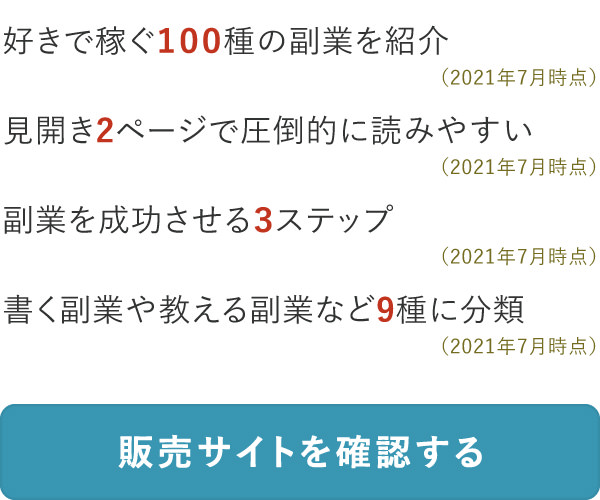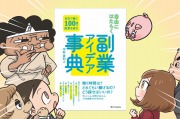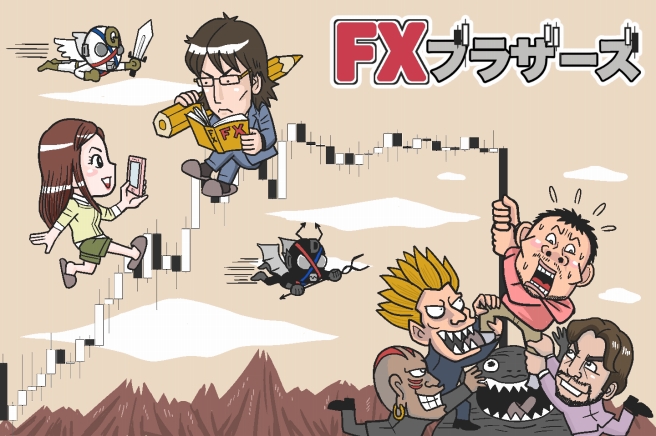住宅ローンでフラット35がおすすめの理由!将来性・低年収OK・手数料0円など


低金利のフラット35を比較
フラット35の金利ランキング
フラット35とは「割安な固定金利が長期間続く住宅ローン」の名称です。独立行政法人である住宅金融支援機構が資金を供給して、ARUHIや楽天銀行といった多数の民間金融機関で申し込めます。
ただし、同じフラット35でも金融機関で金利が異なり、さらに返済期間で金利は上下します。そのため、平均的な条件である「新規借り入れ、借入額3000万円、借入期間21~35年」を軸に、大手で低金利のフラット35のみを比較しました。
| 社名 | 新規借入 | 金利 |
|---|---|---|
| ARUHI | スーパーフラット6S 団信なし・自己資金40%以上 | 年0.540% |
| 楽天銀行 | フラット35S 団信なし・自己資金10%以上 | 年0.770% |
| セブンデイズプラザ りそな銀行 | フラット35 団信あり・自己資金10%以上 | 年1.270% |
| みずほ銀行 | フラット35 団信あり・自己資金10%以上 | 年1.270% |
| イオン銀行 | フラット35 団信あり・自己資金10%以上 | 年1.530% |
![]() 情報取得日 2020年1月時点
情報取得日 2020年1月時点
次にすでに住宅ローンを組んでいる人向けに、借り換えタイプのフラット35の金利を比較してみます。
| 社名 | 借り入れ | 金利 |
|---|---|---|
| ARUHI | スーパーフラット借換 団信なし・自己資金40%以上 | 年0.940% |
| 楽天銀行 | フラット35 団信なし・自己資金10%以上 | 年1.070% |
| セブンデイズプラザ りそな銀行 | フラット35 団信あり・自己資金10%以上 | 年1.270% |
| みずほ銀行 | フラット35 団信あり・自己資金10%以上 | 年1.270% |
| イオン銀行 | フラット35 団信あり・自己資金10%以上 | 年1.530% |
![]() 情報取得日 2020年1月時点
情報取得日 2020年1月時点
住宅ローンの正しい選び方
住宅ローンの金利が変動する要因は「長期金利、金利タイプ、返済期間、自己資金比率、団信有無、借入総額、長期優良住宅、保障内容」などの組み合わせで、何百種類ものラインナップがあります。
そのため、申し込み時に迷いがちですが、基礎知識としては「金利タイプは固定金利より変動金利が低い、ただし変動型は金利上昇リスクがある、返済期間が短いほど低金利、自己資金比率が高いほど低金利、長期優良住宅は低金利」は共通しています。
2020年時点では目先の金利のやすさで「住宅ローンに変動金利を選ぶ人」の割合が多いですが、将来金利が変動して高くなるリスクがあっておすすめはできません。
長期で住む持ち家であるがゆえに、長期的な安心感が得られる固定金利が本来は推奨されています。その上で10年後や15年後に年収が上がる可能性が高かったり、貯金があって金利変動に強い人は「最初の10年のみ固定型」にするなど、変動型の期間を増やすことをしましょう。
注意点としては、店頭や広告に掲載されている金利は表面金利であり、保証料や手数料などが加算されていません。そのため、住宅ローンではすべての支払い額に対する実質金利で比較することも大切です。
実質金利=表面金利+保証料+手数料+団体信用生命保険料


メリットは固定・安心・低い金利
固定金利はライフプランが明確
住宅ローンは変動型のほうが金利が安いために支出は減らせますが、それは現時点の金利によるシミュレーションです。仮に金利が1%から2%に上がると、返済する利息分も2倍になってしまいます。
その点、フラット35は今後35年間の金利が一定に保たれるため、金利の上昇を懸念することなく、住居費が固定化できて、ライフプランが立てやすいです。住宅とは「安心を買うこと」ですので、住宅ローンも同じ考えです。
現在、金融機関ではフラット・シリーズを前面に押し出す傾向が見られ、多種多様な不動産市場のニーズに対応できるように多様化されています。
例えば、20年以内の返済で金利が下がるフラット20、長期優良住宅で金利が下がるフラット35S、最長50年の全期間固定金利であるフラット50、中古住宅をリフォームする際のフラット35リノベなどがあります。
低い年収の人でも借りられる
フラット35を借りるときの条件に年収はありません。つまり、どんなに低い年収の人でも定職に就いていれば、借り入れはできます。年齢、性別、企業名、勤続年数、自営業者などの条件も問われないです。
ただし、借りられる金額は年収によって異なります。フラット35では年収400万円未満の人は年間の合計返済額が年収の30%以内、年収400万円以上の人は年間の合計返済額が年収の35%以内に制限されています。
年収400万円×35%=年間140万円以下の返済額
例えば「夫の年収が500万円、妻の年収が250万円、毎月返済額が10万円、返済期間が35年、金利が1.5%」の場合は、3878万円まで借りることができます。これは住宅金融支援機構による計画的で無理がない金額です。
また、フラット35の対象年齢は申し込み時に70歳未満、完済年齢は80歳までと定められています。一方、親子で住宅ローンを引き継ぐ親子リレー返済では後継債務者を決めることで、満70歳以上での申し込みができます。
質の高い住宅は金利引き下げ
購入する新築住宅における「省エネルギー性、バリアフリー性、耐震性、耐久性・可変性」が一定水準に達していると、5~10年間の金利が年0.25%も下がるフラット35Sが適用されます。
中古住宅をリフォームする場合でも住宅性能が向上した場合は同じく5~10年間の金利が年0.6%も下がるフラット35リノベが適用されます。
保証料と繰上返済手数料は0円
フラット35では保障料が0円であり、保証人も不要です。また、繰り上げ返済時や返済方法の変更による手数料も0円です。ボーナスや副収入でまとまった資金が手に入ったときも、気軽に繰り上げ返済が利用できます。
住宅金融支援機構に相談できる
フラット35を運営する組織は、国土交通省と財務省所管の独立行政法人である住宅金融支援機構です。1950年に住宅金融公庫として発足して、民間金融機関の住宅ローンが受けにくい個人でも住宅が取得できるよう、長期的に低い固定金利の住宅ローンを提供してきました。
民間金融機関が住宅ローンを貸し出し、その返済が厳しくなったときは、個人の債権を住宅金融公庫が買い取ることもあります。民間金融機関が資金回収できないリスクを低くして、間接的に住宅ローンの支援もしてきました。
その後、民間金融機関による住宅ローン市場の拡大から、住宅金融公庫は住宅金融支援機構に名称を変更して、事業を縮小しました。現在は直接融資であるフラット35のみを強化して、民間金融機関経由で事業展開しています。
政府が個人の住宅購入を支援する組織であるため、仮に「急なリストラで返済ができなくなった」や「子供の留学によって返済プランを変更したい」などの相談にも、親身にサポートしてくれる安心感は魅力的です。
デメリットは条件次第で高い金利
頭金なしの人は金利が上がる
フラット35では住宅ローンの融資額が建物価格の90%以上の人は、90%未満の人よりも追加で0.4~0.5%金利が上がってしまいます。つまり、頭金を10%以上用意しない人は、民間の住宅ローンのほうが安いです。
また、新規借り入れではフラット35のほうが金利は有利ですが、借り換えでは民間の住宅ローンのほうが金利は安いです。
金利が上がらないときは不利
フラット35は固定金利のために安心ですが、金利が下降したときは相対的に損をします。金利が1.0%のときにフラット35に申し込んだあと、金利が0.5%に下がっても、フラット35の金利は1.0%のままです。
もちろん、金利が上昇したときは得をするため、例えば「現在の金利が1.0%台と低水準で、下がっても0.5%、むしろ数年後に数%上がる可能性のほうが高い」という判断ができるときはフラット35が有利です。
長期的価値がある物件が対象
フラット35は年収に関係なく借りられますが、長期的に住むために耐震性や耐熱性といった技術基準を満たす必要があります。仮に住宅が技術基準を満たさない場合はフラット35は利用できません。
また、技術基準の審査は検査機関に依頼して、適合証明書を発行されてから貸し付けが始まります。つまり、フラット35の融資は引き渡し時になるため、注文住宅で土地代や着工金が必要な人はつなぎ融資が必要です。