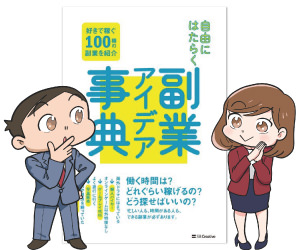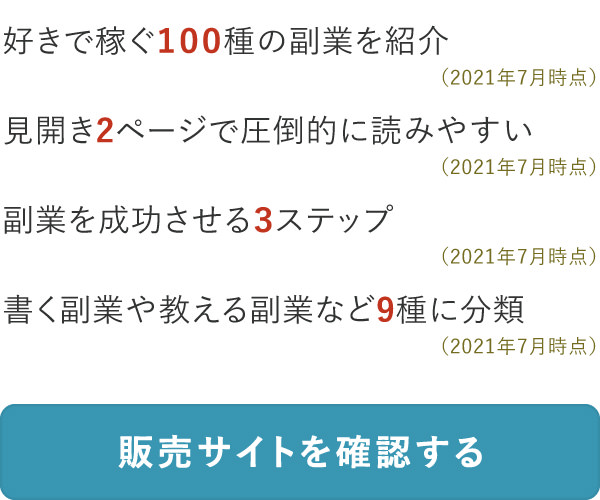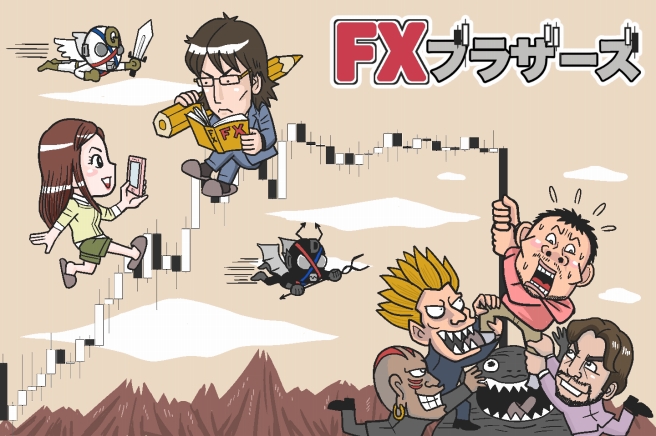金投資の利益にかかる税金はいくら?所得税・相続税・贈与税の計算式


金地金・純金積立・金ETFで税の計算式が違う
金地金の確定申告
金地金の所得税は総合課税で計算します。総合課税とは給与や副収入、雑所得と合算する方式です。そのため、給与が高い人ほど、金地金の利益にかかる税金も高くなります。ちなみに株や不動産は分離課税で税率は一律です。
例えば、金地金の課税所得が100万円の場合、年収400万円の人なら所得税率は10%ですが、年収600万円の人なら所得税率が20%に増えます。
ただし、譲渡利益の計算では「売却価格-取得価格」のみではなく、売却時のコストも引けます。また、金地金の所有期間が5年以内と5年以上では、次のように所得税額の計算式が違う点にも注意です。
①譲渡利益=売却価格-(取得価格+売却コスト)
②課税所得=①譲渡利益+他の譲渡利益-特別控除50万円
③所得税額=(給与などの所得+②課税所得)×税率
①譲渡利益=売却価格-(取得価格+売却コスト)
②課税所得=(①譲渡利益+他の譲渡利益-特別控除50万円)÷2
③所得税額=(給与などの所得+②課税所得)×税率
①譲渡利益ではなく、②課税所得を給与などに足すことがポイントです。ちなみに金地金に固定資産税はかかりません。消費税は購入時に支払い、売却時に受け取りますが、個人に消費税の納付義務はありません。
純金積立の確定申告
純金積立で毎月購入している金融商品は金地金であるため、所得税の計算も金地金と変わりません。給与や他の雑所得と合算する総合課税で計算します。
譲渡利益の計算も金地金とほとんど同じです。売却価格からは取得価格のみではなく、購入手数料や年会費も引けます。また、所有期間が5年以内と5年以上では、課税所得の計算式が違う点も同じです。
①譲渡利益=売却価格-(積立額+年間総コストの合計)
②課税所得=①譲渡利益+他の譲渡利益-特別控除50万円
③所得税額=(給与などの所得+②課税所得)×税率
①譲渡利益=売却価格-(積立額+年間総コストの合計)
②課税所得=(①譲渡利益+他の譲渡利益-特別控除50万円)÷2
③所得税額=(給与などの所得+②課税所得)×税率
積み立て型の所有期間は、先に取得したものから算入します。
例えば、2001~2020年に毎月1万円を積み立てると、20年間で240万円になります。実際に所有している純金が50gあり、その価値が300万円相当まで上がっていたとき、譲渡利益は「300万円-240万円」です。
ただ、ここで半分の120万円分のみを売却するなら、2001~2010年が対象になるため、所有期間5年超えに当てはまり、課税所得は割安になります。
ちなみに純金積立に固定資産税はかかりません。消費税は購入時に支払い、売却時に受け取りますが、個人に消費税の納付義務はありません。
金ETFの確定申告
金ETFは「金上場投資信託」であるため、株式に該当します。株式は分離課税の対象であり、税率は一律20.315%です。
①譲渡利益=売却価格-(取得価格+手数料)
②課税所得=①譲渡利益
③所得税額=②課税所得×20.315%
また、金鉱株・貴金属関連株、金投資信託、金CFD、金先物取引、金限日取引といった金投資も税率は一律20.315%です。FX、金CFD、金先物取引、金限日取引はデリバティブ取引のため、損益通算もできます。
純金積立の贈与税は0~55%
純金積立では生前贈与することで節税ができます。贈与のメリットは贈与税には基礎控除が110万円あることです。つまり、贈与する純金が毎年110万円以下であれば、納税対象にはならず、納税額は0円で済みます。
これを利用して親から子または孫に贈与すれば、仮に相続人の死亡日までに贈与が完了しなくても、贈与した分の相続財産が減ることになり、相続税の節税にもなるわけです。
ただ、純金積立や金ETFはともかく、金地金の場合は1kgあたり600万円前後もするため、年間の贈与額が110万円以上になる人もいます。その場合は以下の表に当てはめて計算します。
特例(父母や祖父母などの直系尊属から20歳以上の子や孫への贈与)
| 基礎控除後の課税総額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 200万円超~400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円超~600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円超~1000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1000万円超~1500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 1500万円超~3000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 3000万円超~4500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4500万円超 | 55% | 640万円 |
一般(特例以外)
| 基礎控除後の課税総額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超~1000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1000万円超~1500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 1500万円超~3000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3000万円超 | 55% | 400万円 |
純金の贈与では贈与成立日の店頭小売価格が評価額となります。贈与税は受け渡し日が曖昧になりやすいため、契約書を交わすなど、贈与の成立日が判るようにしておくことで、税務署との諸問題も発生しにくくなります。
ちなみに贈与者が贈与してから3年以内に死亡した場合は、その贈与が相続と見なされてしまい、贈与税ではなく相続税の対象になります。
純金積立の相続税も0~55%
相続税は親族などが死亡したことにより、財産を譲り受けた者に発生する国税です。遺言による遺贈(いぞう)も同じく相続税がかけられます。
純金積立を始めとした金投資も財産にあたりますので、相続税の対象です。相続税は課税対象の遺産が多くなるほど税率が高くなる累進課税であり、税率は10~55%です。
ただし、相続税にも基礎控除があります。基礎控除の計算式は以下の通りであり、遺産から基礎控除を引いた課税遺産総額が納税対象となります。
①基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
②課税遺産総額=相続対象となる課税価格-①基礎控除額
そのため、相続人の人数にもよりますが、相続税の納付は相続対象となる課税価格が最低3600万円を超えたときです。その場合は以下の表に当てはめて計算します。
| 基礎控除後の課税総額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1000万円以下 | 10% | - |
| 1000万円超~3000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3000万円超~5000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7200万円 |
純金の相続では死亡日の店頭小売価格が評価額となります。例えば、被相続人が死亡した日に相続人が純金を受け取った場合、死亡日の店頭小売価格が評価額になります。
仮に8000万円もの純金が相続対象になり、相続人が妻と子供1人であったとします。そのときの相続税の基礎控除額は4200万円です。
3000万円+(600万円×2人)=4200万円
基礎控除後の課税総額は「相続対象-基礎控除」で3800万円になり、妻と子供で1/2ずつに分けると、1人1900万円です。
(8000万円-4200万円)÷2人=1900万円
それを前述の表で計算すると、1人あたりの相続税額は285万円になります。2人では570万円であり、相続人が多いほど相続税額は少なくなります。
(1900万円×15%)-50万円=285万円
このように8000万円の純金を2人に相続しても1人285万円です。その結果、金地金ならありえるかもしれませんが、純金積立では「月10万円×数十年間」という金額を積み立てないと相続税は発生しません。