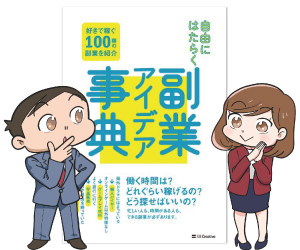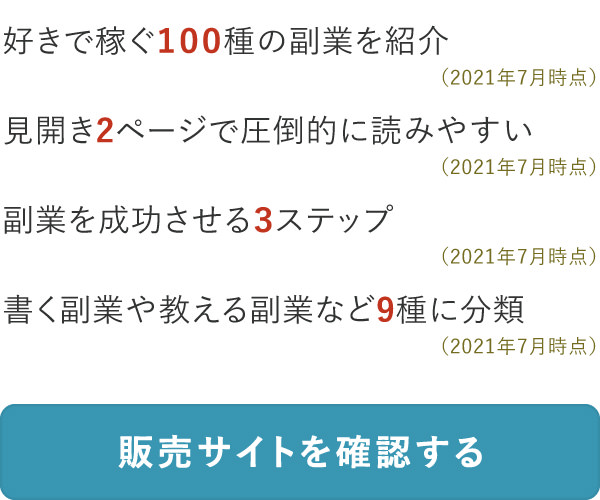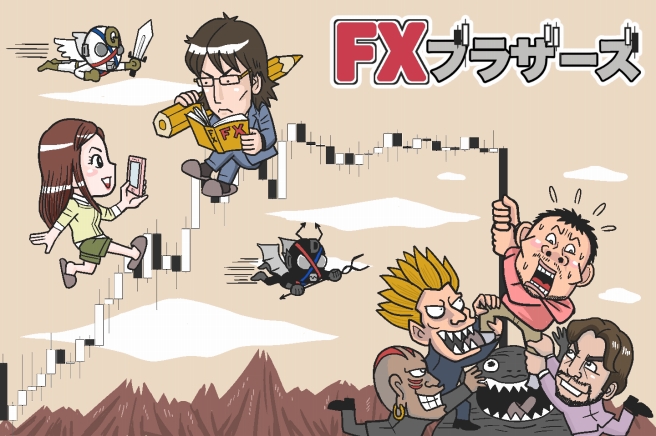1人暮らしの食費の節約術6選!平均額の月3万9649円は買い物上手でもっと下がる


食費は工夫次第で節約できる支出です。昼食は1000円の外食を弁当にして年間19万2000円、自動販売機のドリンクは水筒にして年間7万2000円、飲み会月5回を1回にして年間24万円、それ以外の細かい節約を合計すると年間50万円減ります。
- 1人暮らしの食費は月平均3万9649円
- 節約① 買い物リストで衝動買いを防ぐ
- 節約② 旬の時期に割安な食材を買う
- 節約③ 保存できる割安な食材を買う
- 節約④ 冷凍できる割安な食材を買う
- 節約⑤ 弁当で月1万6000円節約できる
- 節約⑥ タイムセールで30~50%引きになる
1人暮らしの食費は月平均3万9649円
総務省の2017年の「家計調査」によると、食費の平均値は1人世帯で月3万9649円、2人世帯で月6万4730円、3人世帯で月7万4716円でした。
ただ、食費は節約術の中でも特に工夫が必要です。年収1000万~1200万円の高所得世帯でさえ、貯金0円が20.3%※1もいるように、食費を抑えないと一向にお金は貯まりません。
※1 金融広報中央委員会(2016年)「家計の金融行動に関する世論調査」
節約① 買い物リストで衝動買いを防ぐ
最も無駄な支出の1つに「衝動買い」があります。衝動買いは商品が急に欲しくなって「今しか買えない」と思い込み、自制が効かなくなる状態です。ただ、本来は必要のないものであり、無駄遣いに過ぎません。
食品も同じです。1つの金額が小さいために衝動買いに気づきませんが、日常的な無駄が積み重なっては大きな出費に膨らみます。突然の「ピザを頼もう、飲み会が続く、コンビニに寄ろう」も衝動買いの一種です。
この余計な物を買いたくなる衝動を防ぐためには、事前に「買うものと食費の予算」を決めましょう。買い物リストにないものは基本的に買う必要がないですし、食費の予算がオーバーしたら節約を意識できます。
普段から食費の少ない人は、プランニングができています。食材を余らせることなく、保存や冷凍で廃棄を防ぎます。旬の食材と適正価格を知っていて、タイムセールで買った食材で、弁当を手作りするわけです。


節約② 旬の時期に割安な食材を買う

旬とは「食材の収穫期」を意味します。ハウス栽培や輸入品、養殖が増えたことで旬が見えにくいですが、旬の時期に入ると流通量が着実に増えて、全般的に価格が下がりやすいです。しかも、新鮮で味も安定しています。
つまり、旬の時期を知りつつ適正価格を覚えれば、おいしくて食材を安価で手に入れることができます。まずは「今の時期に割安な食材を知る、スーパーの特売日を知る、特売でよく扱う食品を知る」ことが節約の第一歩です。
例えば、メカジキは年中店頭に並んでいますが、三陸産は12~2月が最も脂が乗っています。魚類の値引きは早めの20時に始まるスーパーが多く、50%オフでも購入できます。1人暮らしなら会社帰りに割安で買えます。
ちなみにいくら特売品でもおいしくない食材が続けば、節約する気持ちもなくなっていきます。そこである程度は鮮度を見分ける知識を付けておくことで、日常的にも役立ちます。
| 食材 | 見分け方 |
|---|---|
| 牛肉 | 鮮紅色、脂肪が淡い黄白色な肉ですと質が良いです。 |
| 豚肉 | 淡紅色で脂肪が真っ白で肉との境目が明瞭なものが新鮮です。 |
| 鶏肉 | 淡紅色でギュッと引き締まっているようなものがおいしいです。 |
| 魚介類 | 目が透明で澄んでいることです。さらに体に弾力があり、模様や色が鮮やかである方が好ましいです。 |
| 根菜 | 泥付きの方が鮮度キープされています。大根などの葉が付いている野菜は、葉の部分のみずみずしさをチェックします。 |
| 葉菜 | 緑が濃くてみずみずしいことです。切り口が乾燥していたり、しんなりして変色していたら、買うのは控えます。 |
質が悪い食品は保存期間も短くなってしまい、食材が使い切れずに無駄になりやすいので、安い良品を見分けられるようになりましょう。


節約③ 保存できる割安な食材を買う
食材は特売日にまとめ買いが節約の基本です。その中でも保存食はまとめ買いしても長期保存によって廃棄率が低く、メニューもたくさんあり、緊急事態にも困りません。食費を抑えたい月に使える融通の利く食品です。
| 保存食 | 保存期間 | 見分け方 |
|---|---|---|
| 米・パスタ | 1年 | 電子レンジによる調理が便利です。ご飯は1人分なら炊けますし、パスタも専用容器に入れて茹でることができます。 |
| 小麦粉 | 1年 | 粉物は低単価で保存が利きます。酸化による劣化を防ぐため、空気を抜いてビニールに密封すると1年以上持ちます。 |
| 乾麺 | 1年 | 主食になる定番の保存食です。そうめんなどは1年未満で風味が落ちるため、買う時期は夏前に絞るなどタイミングも意識します。 |
| いも類 | 2~6カ月 | 新聞紙にくるみ、ポリ袋の口を軽く閉じて、冷蔵庫の野菜室に保存すれば、じゃがいもは6カ月、さつまいもや長芋は2カ月持ちます。 |
| 根菜 | 1カ月 | 玉ねぎやごぼうは土の中で長持ちします。それが難しい場合はなるべく土がついた状態で、新聞にくるんで冷暗所に置くと1カ月は持ちます。 |
| 葉菜 | 1カ月 | 昔は残った野菜は漬物にすることが多いですが、今は冷凍庫が発達しており、ほとんどの野菜を冷凍することもできます。 |
| 缶詰 | 2~3年 | 開封前なら長期保存できる缶詰はストック数を決めます。古いものから使いながらスーパーの特売時に買い足すようにします。 |


節約④ 冷凍できる割安な食材を買う
ご飯はもちろん、肉や魚の冷凍保存も一般的です。多く作ってしまったシチューやカレー、トマトソースは常温では1日、冷蔵では2~3日が限度ですが、ビニールパックに入れて保存しておけば、1カ月は持ちます。
食品はすばやく冷凍するほど味が保てるため、一旦、常温で熱気を取り除いてから、冷凍庫の冷気のあたりやすい場所に入れて、急速冷凍しましょう。
野菜はラップに包んでから、ジップロックなどのフリーザーバッグで保存します。基本的には空気と水気を抜くことで、1~2カ月持ちます。例えば、きゅうりなら塩で揉んで水分を絞ると、長期保存できます。
すべての野菜は下ごしらえと調理次第でおいしく冷凍できます。にんにくや生姜、ねぎなどは刻んだ状態で冷凍してもOKです。特に解凍しなくても使えて、料理の味を深めてくれます。
また、スーパーではあらかじめ冷凍されている野菜も販売していますが、こちらは割高です。冷凍技術を駆使することでコストパフォーマンスが上がります。


節約⑤ 弁当で月1万6000円節約できる

SBI新生銀行の2024年6月時点の「2024年会社員のお小遣い調査」によると、会社員の1回あたりの昼食代は男性が709円、女性が694円でした。月20日出社するなら1カ月で1万4000円前後、年間では17万円程度です。
しかし、会社が都心にあって昼食に1000円近くかかるなら「1000円×20日×12カ月=24万円」です。逆に手作り弁当にした場合は「200円×20日×12カ月=4万8000円」で済み、外食よりも19万2000円も節約できます。
毎日できなかったとしても、半分の10日でも年間9万6000円の節約にあるため、わりと昼食は手作り弁当という人が多いわけです。
手作り弁当を続ける基本は、前日の残り物と3~5品の常備している冷凍食品の組み合わせです。さらに卵焼き、ソーセージ、冷凍ブロッコリーなどの加工食品で種類を増やします。
ご飯も冷凍したものをレンジで加熱して入れれば、炊かなくてもOKです。忙しい人は冷凍おにぎりでも構いません。休日にまとめてご飯を炊き、おにぎりを作り、のりは付けずにラップで包んで冷凍します。
飽き防止のためには「ふりかけのストックが数種類、ご飯に混ぜるタイプのふりかけ、梅干しや鮭、ご当地のごはんの友、炊き込みご飯」などを用意すると楽しみが増えます。
あとは食べる日の朝、もしくは職場の電子レンジでご飯を加熱して、さらに3品程度の惣菜かおかずを持っていけば、立派なお弁当です。
さらに弁当箱に加え、水筒を持参して、自動販売機を使用しないことを心掛けましょう。毎日2本のドリンクは「300円×20日×12カ月=7万2000円」にもなり、節約しがいがあります。


節約⑥ タイムセールで30~50%引きになる
食費を抑えるためには、会社帰りの時間に値下げする店舗を利用することが有効です。スーパーのタイムセールは刺し身や惣菜を中心に30~50%も安くなり、帰りが遅い会社員にはありがたい仕組みです。
大型チェーンのスーパーでは独自のポイントシステムを発行しているところもあります。買い物で1%安くなったり、ポイントで1%の特典が貰えたりします。年間で60万円の買い物をする店舗なら、実質6000円の得です。
チラシなどで1番安い店をチェックすることも大切です。卵が特売で70%オフは当たり前ですし、他店競合が近くにあるほど値引き額も大きいです。
また、昼食や夕食問わず、官公庁や大学が近くにあれば、誰でも入れる格安の食堂として使えます。1食500円もかからずに栄養バランスに優れたおいしい食事が毎日食べられます。