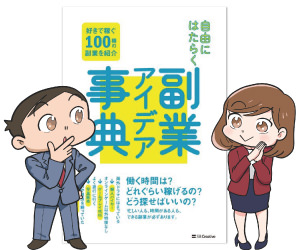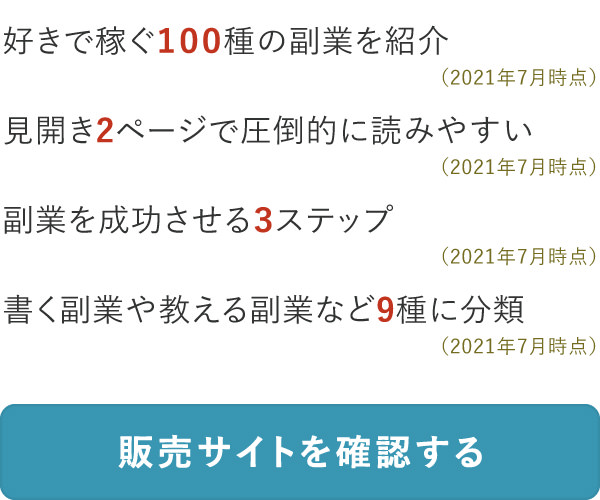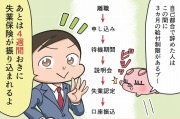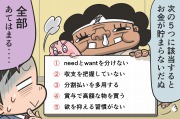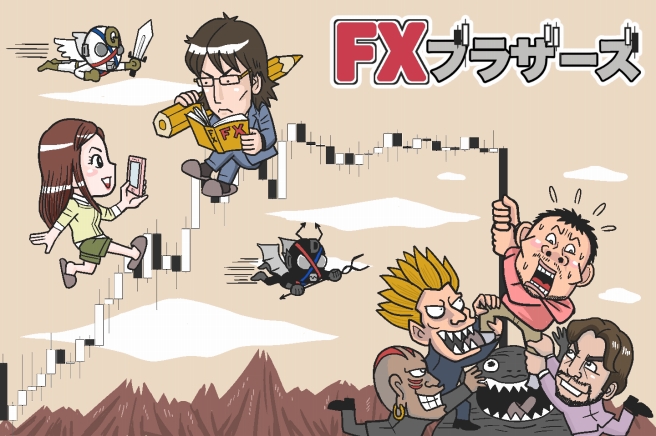少ない収入でお金を貯める方法!3ステップで年間100万円


みんなの平均貯蓄額を知る
金融広報中央委員会の2019年11月の「家計の金融行動に関する世論調査」によると、預貯金や株式などの金融資産の保有額は、1人暮らしの人が平均645万円、2人以上の世帯が平均1139万円でした。
![]() 金融広報中央委員会(2019年)「家計の金融行動に関する世論調査」
金融広報中央委員会(2019年)「家計の金融行動に関する世論調査」
ただし、2019年の調査では3222世帯の中に、金融資産の保有額が2000万~3000万円未満が213世帯、3000万円以上が286世帯含まれており、彼らが平均を押し上げています。
逆に金融資産の保有額が0円の人が761世帯もいて、その割合は1人暮らし世帯で38%、2人以上の世帯で23.6%に達するほどです。
そのため、平均値のみでは現状把握ができないことから、全員を金額順に並べた中央値を見たほうが実感に近いです。その結果、1人暮らし世帯では45万円、2人以上の世帯では419万円が中央値となりました。


同様に年代別の平均貯蓄額も、平均値と中央値ではかなりの差があります。例えば30代は平均値が470万円ですが、中央値は200万円になりました。
| 年代 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|
| 全年齢 | 1139万円 | 419万円 |
| 20代 | 165万円 | 71万円 |
| 30代 | 529万円 | 240万円 |
| 40代 | 694万円 | 365万円 |
| 50代 | 1194万円 | 600万円 |
| 60代 | 1635万円 | 650万円 |
| 70代以上 | 1314万円 | 460万円 |
![]() 金融広報中央委員会(2019年)「家計の金融行動に関する世論調査」
金融広報中央委員会(2019年)「家計の金融行動に関する世論調査」


ちなみに金銭的理由で「老後の生活が心配である」と答えた人は、1人暮らし世帯で84.9%、2人以上の世帯で81.4%に達しており、なるべく若いうちから貯金をして、お金の心配をなくしたい傾向が見られます。


ステップ① 目標を決めてやる気を出す
将来のための目標を決める
数十年先の老後生活を見越すことは大切です。ただ、貯金をするモチベーションとしては、不透明感が強く現実味に欠けます。そのため、まずは向こう10年後までに起きるイベントで、将来設計をしてみましょう。
- やりたいことや予測できるイベントをリスト化します。
- リストの項目ごとに必要な金額を調べてみます。
- それらに優先順位を付けて、本当に必要な項目を抽出します。
- 各目標で達成したい時期を決めます。
- 内容、金額、時期がわかったら、メモなどに書き留めます。
完成した目標設定リストは想像していたよりも、莫大な金額が書かれているかもしれません。しかし、今から貯金をすれば、決して不可能な金額ではなく、目標が見えただけでも実現する確率は高まっています。
住宅・子供・老後で区切る
目標設定リストは年齢と個人で中身が異なってきます。毎日の生活費とは別に「結婚をしたい、マイホームを買いたい、子供が欲しい、老後に備えたい」など、大きな支出も出てくるでしょう。
ただ、このようなライフプランが見えにくい人は「人生の3大資金」である住宅、育児、老後を1つのステージと捉えて、そのステージでは「何を希望して、いくら必要になるか」を考えます。
例えば、住宅を購入するステージなら「一軒家が欲しい、場所は会社から電車で40分以内、車はローンなしで購入したい、住宅ローンは20年以内に完済する」というように、細かい希望を重ねていきます。
その結果「物件価格の30%は頭金を準備しなくてはいけない、頭金を多いほど利息分がかなり得になる、20年返済では月15万円は支払う」などと気付くことが増えて、それがお金を貯める動機になります。
目標は短期と長期に分ける
通帳口座を目的別に分けることも理にかなっています。例えば、海外旅行の30万円と住宅購入の300万円を貯める場合、それぞれ専用口座を開設して、毎月数千~数万円ずつ入金していく人もいます。
しかし、年齢を重ねるに連れて、子供の養育費、自家用車の代金、老後の資金など、目標設定リストは増えていき、その結果、貯蓄が分散しすぎると貯まる実感が乏しく、挫折しやすいです。
そこで貯金をするときは短期と長期の2タイプに分けます。例えば、短期では3年以内に使うお金を貯めて、目標も30万円以下にします。長期では3~10年以上あとに使うお金を貯めて、目標は30万円以上とします。
あえて使途を明確にせず、短期と長期のみに分けることで貯まる実感が得られます。また、長期の預金は数年間は使わないため、普通預金ではなく、定期預金や投資信託、社債などに投資することもできます。
ポジティブ思考で貯金する
貯金とは倹約の精神を保ち、ストレスに耐え続ける苦行ではありません。貯金が続いている人の共通点は「我慢している感じがしない、貯金が習慣化している、むしろ貯金を楽しんでいる」ことです。
これができる理由は将来を見据えた目標を決めているからです。つまり、理想的な未来をイメージして、その過程として貯金があるため、お金を貯める行為に対してもポジティブな思考を持っています。
私たちも目標設定をすることで、貯金をしたくなる意識が芽生えます。特に「結婚資金を300万円貯めたい、タワマンを買うための頭金が1000万円欲しい、海外旅行の費用を50万円捻出したい」などです。
ステップ② 収入と支出を正しく把握する

労働政策研究・研修機構の「ユースフル労働統計2016」によると、生涯賃金の平均は男性が大卒で2億7000万円、高卒で2億1000万円、女性が大卒で2億2000万円、高卒で1億5000万円でした。
一方で生涯支出は「22~64歳の生活費が1億4548万円、結婚関連費用が513万円、子供の学習費が2人で986万円、マイホームが首都圏の建売住宅で3538万円、マイカーが1500万円、生命保険が964万円、老後の平均生活費が5760万円、税金が5400万円」で、合計3億4000万円となります。
大卒の男性でも約7000万円も足りません。老後は年金が4800万円貰えますし、配偶者も働くことで赤字は免れますが、それでも若いときに贅沢や散財をしたり、突然の病気や介護によって、支出は簡単に増えていきます。
特に20代は住宅や介護といった大きな支出がなく、1人分の生活費で済むために自由に使いがちですが、老後で詰まないためにはなるべく早くから毎月の支出を見直して、貯金する習慣が不可欠です。
会社員であれば、基本的には1年おきに給料は上がっていきます。それでも貯金ができない人は、欲が先行してしまって不要な支出が増えているため、それらを把握することから始めましょう。
やりかたは簡単です。まずは支出を家計簿にすべて付けます。家計簿は手書きのノートは計算ミスを招くためにやめます。家計簿ソフトもパソコンを起動することが面倒であり、レシートをなくしたら漏れが出ます。
ベストはマネーフォワードやZaimといったスマホの家計簿アプリです。手順は「支払いをクレカや電子マネーに集中する」のみで、あとは家計簿アプリが自動的に分類してくれます。これですべての支出がグラフ化されます。
次にその支出を「①固定費、②消費、③浪費」の3つに分けます。①固定費は家賃、水道光熱費、通信費などで、毎月決まった支出です。ここを見直すことで抜本的に支出を減らすこともできますが、基本的には固定です。
②消費は食費、日用品、交通費、衣服、美容、交通といった変動費であり、その中でも必要とされる支出です。ここを減らすとストレスがかかるため、毎月の限度額を決める程度に留めておきます。
③浪費が今回のポイントです。例えば、コンビニで買ったスナック菓子や衝動買いしたジャケットは、購入する計画があったわけではない不要品です。これらをばっさりと切り捨てることで着実に貯金が増えます。
年収1000万円以上の会社員でも食事は外食、車は外車、自宅はタワーマンション、子供は市立通い、高級バッグも何個も持っているでは、貯金はできません。消費と浪費の違いを見極めることが私たちには必要です。
ステップ③ 貯蓄術を15個から選ぶ
目標を10年分決めたことで貯金する意志が固まり、収支を正しく把握したことでお金を貯める準備が整いました。ここでようやく貯蓄術を選び、それらを実行していきます。有名な貯蓄術は次の15個です。
- 先に貯金をしてから支出する。
- 会社の財形貯蓄や持株制度で、給与から天引きしてもらう。
- つみたてNISAによる自動引き落としで投信積立に資産を移す。
- 個人型確定拠出年金のiDeCoに加入して、税額控除を受ける。
- 貯金専用の口座を作り、引き出さない。
- 賞与は使う前提ではなく、すぐに全額預金に移す。
- おつりアプリでおつりを貯める。
- つもり貯金で使わない分を貯める。
- 買うものは事前にメモして、それ以外は買わない。
- 自分へのご褒美はお金に頼らない。
- 住宅購入以外のローンは絶対に組まない。
- クーポンを使うなどの小さな工夫の連続で、節約が習慣化される。
- お金のかからない趣味をする。
- 副業をして支出する時間を減らす。
- 年1回は断捨離をして、不要品をメルカリで売る。
おつりアプリとつもり貯金がおすすめ
おつりアプリは「スマホにアプリをインストール、銀行口座やクレカを登録する、決済手段と金額を設定する、設定した決済手段で買い物をする、おつりが自動的に貯金用口座に移動する」という仕組みです。
例えば「1000円単位でおつりを貯める」としたとき、800円のランチを食べると「1000-800=200円」が貯金用口座に貯まります。意識的に貯金できないなら自動化することが最適解です。
おつりアプリは家族で一緒に貯められるフィンビー、マネーフォワードが運営するしらたま、おつりを東進で運用できるトラノコがメジャーです。
つもり貯金は例えば、毎日のカフェ代が300円のとき、そのコーヒーを我慢して、300円を使ったつもりで貯金します。勤務中の自販機のドリンクや会社帰りのコンビニのアイスでも構いません。
つまり、我慢するのではなく「この前も買った」と錯覚することで、ストレスを軽減することが狙いです。つもり貯金の手順は小さい貯金箱と大きい貯金箱を用意して、置く場所を工夫することから始めます。
小さい貯金箱につもり貯金を入れていきます。小さい貯金箱がいっぱいになったら金額を確認して、大きい貯金箱に移します。また、小さい貯金箱への貯金を繰り返すことで、いつの間にか数万円単位で貯まっていきます。
年間100万円を貯めた人の体験談や口コミ


年間110万円
独身時代は給料をそのまま遊びに使っていましたが、結婚を決めたと同時に「貯金をしないとかなり不安」ということにようやく気づきました。コツは「予算を袋分けに管理する」ことです。
貯金を開始する前までは、給料から生活費を引いたほとんどが「本、CD、DVD、ゲーム、スノボー、旅行」といった娯楽に消えていきました。
しかし、結婚を決めた段階になって、将来を考えるようになります。結婚式の費用、住まい、出産や育児を考えると、生涯を通しての資金がないことに気づいたために、非常に焦ったことを覚えています。
そこで「将来の家族のために貯金を必ずする!」と決意を固め、彼女と家族に協力してもらっての節約生活が始まりました。
まず、家計簿を付け始め、1カ月付けている間に節約術の情報を収集し、2カ月目から光熱費の節約を実践し始めます。家計簿の項目ごとの大体の支出額が把握できるようになったので、3カ月目には1カ月の予算を決めました。
水道光熱費や電話などは自動引落に切り替え、余計な手間がかからないようにもします。それ以外の生活費は大別した予算ごとの封筒を作るようにして、お金を分配することにしました。
4カ月が経つと、光熱費が下がっていることが実感します。少しの意識の違いで数千円単位で変わってくるものです。その下がった分は貯金をすることにし、さらに自動積立もできるようになりました。
また、予算の袋分けをしたことによって無駄な買い物をカット、カットした分をつもり貯金にして、小銭を専用の貯金箱に入れていきました。大別した予算袋で余ったお金も貯金箱に入れていきます。
貯金に加速度がついたのは、この努力を親族が認めてくれ、食料を送ってくれたり、食事に呼んでくれるようになったことです。とても嬉しく思い、感謝をしています。
ただ、節約生活で娯楽も削っていたため、ストレスが溜まったのは否めません。衝動買いをしてしまうこともあったので、貯金の一部に旅行やレジャーを割り当てて、目的意識の持った生活をするようにしました。
また、家計簿を付けるのは始めは面倒でしたが、レシートを貰う癖をつけ、家計簿アプリを駆使しました。そのおかげで貯金スタート1年目で110万円の貯蓄に成功し、今も年間100万円の貯金計画を継続中です。

年間150万円
今は結婚もしていませんが、いずれは専業主婦になって、子育てに専念するという夢のために、年平均で150万円を貯めることができました。目標を設定することで、自然と節制ができるようになります。
私は短大を卒業してから20歳で就職しました。早くから「結婚して、20代で出産したい」と考えていました。
それは自分の家を持ち、料理、洗濯、掃除、育児をこなせる「立派な主婦になりたい」という夢があったため、資金を貯めなければいけないという意識が強かったです。
今は共働きの時代で、もちろん「仕事を続ける」という選択肢も残っていますが、まずは子育てと専業主婦を目指したいタイプであり、子供に手がかからなくなった10歳くらいから「また、本気で働こう」と思っています。
そこで貰った給料を効率良く貯金する方法を探した結果、選んだのが財形貯蓄でした。財形貯蓄は給料天引きで強制的に引かれる上に、会社が管理していて、なかなか崩しにくいのが特徴です。
給料から何とか貯金していくというよりは、知らないうちに自然に貯金が貯まったという感覚になります。今考えると精神的な負担が少なく、自分に合っていたかもしれません。
大切なのは財形貯蓄を継続しつつ、就職して6年経った今でも、就職当初の収入レベルを生活を続けるように努力し、収入が増えた分は貯金の増額にまわしてきたことです。
さらに財形貯蓄がある程度貯まってきた段階で、もっとうまく増やす方法がないかと調べた結果、財形貯蓄をまとめて金利の高いネット銀行に移管しました。
同時に小額からでも投資を始めようと勉強します。株式やFXなどを調べていくうちに、経済の動きに敏感になっていくのがわかります。今では貯金の一部分は投資に回していて、月に数万円の利益を得られるまでになりました。
節約情報も仕入れるようになり、家賃、生活費、緊急時用、旅行用などといった具合に、口座を目的別に分けて管理することもしています。
また、夏と冬にボーナスが少しだけ支給されるのですが、1度も使わずに貯めてきた結果、6年間で900万円の資産を貯めることに成功しました。